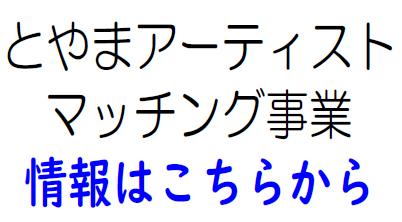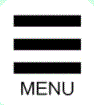〈7〉そして第二回へ
反省会を重ね、座談会で語り合い、簡素な解散パーティを開いたとき、期せずして、これだけの成果を上げたものを一度で止めるのは惜しいという声が挙がった。それも、外野席で、言葉は悪いが汗をかかないで楽しんだ方面からではなく、自ら額に汗し、走り回って基金を集めた人たちからの声であった。第二回を、という話が決まった。
1985年が「国際青年年」であることから、第二回は85年に「富山国際高校演劇祭」として開催することが話し合われ、第一回と同じく、深山会長、小泉事務局長の体制で実行委員会が出来上がったのは、84年の春であった。会期は高校生ということもあり、夏休み中が良かろうとあって、8月1日から5日までとなり、7月31日富山必着の事という条件になった。また、教育的ということもあって、今度は順位をつけないことになった。AITA/IATA組織を利用して、参加団体を募ることにしたのは、ある意味で正解だった。煩雑な手続きと選考の手間が省けるからである。また、国際アマチュア演劇連盟組織に未加入のところについては、小泉氏がそのアジア地区センター代表になっていたこともあり、アジア各国から、祭りに参加するよう招待することになった。劇作家の内村直也氏、日本のアマチュア演劇連盟の原千代海氏、栗原一登氏などが参加し、公演終了後に講評する講師役を務めて貰った。
参加申し込みは海外から12ヶ国となったが、最終的にソ連が参加を取り消したので、11ヶ国、国内から3グループとなった。今回は世界の高校生が集まるということもあって、演劇公演の他に、シンポジウムと討論会での意見交換の場が設定されて、違いを知り、相互理解を深めることが図られた。各公演は、それぞれの国の抱えている問題を描き出そうとする意図が明瞭に窺える力作が多かった。中でも、チェコスロバキアから参加したデフ・シアター・アンサンブルの舞台は、大変な感動を呼び起こした、傑作の一つであった。聾唖者であるから、耳からの科白には反応できない。光りと足に伝わる床の響きがキューになると聞いたが、彼らに聞こえていない音楽と彼らの描く舞台上の影像は完全にマッチして、ただ見ていた人には、到底彼らが聾唖者とは、思えなかっただろう。

世界の若者達と中沖知事

日本一うまい立山の霊水
アメリカからは、歌と踊りの若さ溢れるパフォーマンスを披露したグループ(彼らの多くはブロードウエイを目指しているのだと聞いた)と、ハワイの高校生のバンドを中心としたグループがあった。この時も、ここにはメッセージが無いという批判が聞こえてきた。ブルガリアの高校生は、部活で柔道をやっている少年の家庭問題を扱って好演した。だが、今度の演劇祭で特筆すべきは、何と言ってもクロイニンゲン氏(デンマーク)が行った「高校演劇と放送」と題するスピーチである。その中で、彼は高校教育の中での演劇を考えるとき、最終的に舞台上に演じられる作品の完成度を目指す演劇活動と、最終的成果を生むまでの過程(作品選びに始まって、配役から、照明、効果、小道具、衣装など舞台装置に関わるもの、全てが連携を保ち、関わりあって、創り上げていく過程)を重視する演劇活動があることの指摘である。もちろんこれは、事新しい指摘ではないが、この発言を機会に、最近の技術の進歩で色んな方面での可能性が広がっている中で、矢張り教育という範疇の中で演劇の目指す方向付けに関心があることを伺わせて、興味深いものであった。
第二の興味を引いた点は、これはドイツグループが演じた、舞台全面を四つの枠組みに仕切って、それぞれのなかで現代人が直面する現実の葛藤を描いた実験的作品を巡っての論議である。若者のおかれた現実として描かれた場面に、暴力あり、喫煙あり、またベッドシーンを示す場面ありで、そのリアルな表現に関しての論議である。いわゆる西側の人たちにとって、それは当然の描写であって、当たり前のことであるのに対し、東の人たちにとって、あれほどまでにリアルに描き出す必要は無いというのであった。討論会では西側と東側とで、この問題に対する賛否が違っていた。舞台上のリアリスティックな表現の必要性の強調に対し、では殺人の場面はどうなるのかといった皮肉な言葉も、脇台詞として聞こえてきた。また、某国(メキシコ?)では、喫煙に年齢制限はないという話しも聞いたが、喫煙、飲酒の年齢制限の有無の違いがあることを知ったことも面白かった。ひっくるめて文化の違いということになるのだが、それは何時かは融合し、溶け合って行かねばならないものであろう。(ジュリエットの父は、自分の選んだ男性パリスに娘を娶せようとして、ロメオを恋する彼女を死に走らせることになった。シェイクスピアと、シェイクスピアが日本に紹介された明治との隔たりは、時間にして約三百年。だがそれは鎖国状態でのことだ。現在の日本は欧米の何処と比べても、風俗的にさえ、遅れているところがあるのだろうか?何を以て遅れていると言うのかは、また別問題であるが。)
この富山国際高校演劇祭には、前回同様多くのヴォランティアの参加があった。富山の高校生も、多く、観客として参加したし、舞台に関わる方面にも参加していた。だが、一部で「高校演劇祭」と言いながら、我々高校生の思うようにやらせてくれなかったという不満があったと聞いたが、これは自称ヴォランティアという方々からよく聞く不平である。誤解を招く恐れを敢えて冒して言うのだが、ヴォランティアとして参加される人は、その場に必要な能力を持って初めて「役に立つ」のであり、些かでも力不足であれば、それは全体を崩壊させる原因となるということを、充分に認識して欲しいのだ。時間のあるときは、指導的に補助し、協力していくことはできるのだが、時間に追われ、人手が緊急に求められているとき、その余裕はないし、却って足手まといになる恐れが大きい。諺にもいうではないか、「生兵法は怪我の元」と。最後の仕上げ段階になって出番を求めたり、力不足の方が出てきたいと言われても、それは無理な話なのである。先の教育の中の演劇に倣って言えば、最後の舞台の花道に出たいというのは無理で、全体の過程の中で成長し、育っていって、将来十分力になって行かれることことが望ましいのである。
第二の興味を引いた点は、これはドイツグループが演じた、舞台全面を四つの枠組みに仕切って、それぞれのなかで現代人が直面する現実の葛藤を描いた実験的作品を巡っての論議である。若者のおかれた現実として描かれた場面に、暴力あり、喫煙あり、またベッドシーンを示す場面ありで、そのリアルな表現に関しての論議である。いわゆる西側の人たちにとって、それは当然の描写であって、当たり前のことであるのに対し、東の人たちにとって、あれほどまでにリアルに描き出す必要は無いというのであった。討論会では西側と東側とで、この問題に対する賛否が違っていた。舞台上のリアリスティックな表現の必要性の強調に対し、では殺人の場面はどうなるのかといった皮肉な言葉も、脇台詞として聞こえてきた。また、某国(メキシコ?)では、喫煙に年齢制限はないという話しも聞いたが、喫煙、飲酒の年齢制限の有無の違いがあることを知ったことも面白かった。ひっくるめて文化の違いということになるのだが、それは何時かは融合し、溶け合って行かねばならないものであろう。(ジュリエットの父は、自分の選んだ男性パリスに娘を娶せようとして、ロメオを恋する彼女を死に走らせることになった。シェイクスピアと、シェイクスピアが日本に紹介された明治との隔たりは、時間にして約三百年。だがそれは鎖国状態でのことだ。現在の日本は欧米の何処と比べても、風俗的にさえ、遅れているところがあるのだろうか?何を以て遅れていると言うのかは、また別問題であるが。)
この富山国際高校演劇祭には、前回同様多くのヴォランティアの参加があった。富山の高校生も、多く、観客として参加したし、舞台に関わる方面にも参加していた。だが、一部で「高校演劇祭」と言いながら、我々高校生の思うようにやらせてくれなかったという不満があったと聞いたが、これは自称ヴォランティアという方々からよく聞く不平である。誤解を招く恐れを敢えて冒して言うのだが、ヴォランティアとして参加される人は、その場に必要な能力を持って初めて「役に立つ」のであり、些かでも力不足であれば、それは全体を崩壊させる原因となるということを、充分に認識して欲しいのだ。時間のあるときは、指導的に補助し、協力していくことはできるのだが、時間に追われ、人手が緊急に求められているとき、その余裕はないし、却って足手まといになる恐れが大きい。諺にもいうではないか、「生兵法は怪我の元」と。最後の仕上げ段階になって出番を求めたり、力不足の方が出てきたいと言われても、それは無理な話なのである。先の教育の中の演劇に倣って言えば、最後の舞台の花道に出たいというのは無理で、全体の過程の中で成長し、育っていって、将来十分力になって行かれることことが望ましいのである。

富山国際青年演劇祭開催に尽くした(左から)ジョン・イテボルク、モート・クラーク、 ヒュー・ラブグローブの3氏に中沖豊富山県知事から「とやま名誉大使」の委嘱

深山榮会長とモート・クラーク教授
多感な高校生の集まりで、それだけに共感するところが多いのだろう。別れを惜しんで抱き合う姿が、ほほえましく、また感動的だった。そういった表現方法は流石に西側の人たちはごく自然に、身に付いているようだった。高校生は、半ば大人であり、半ば、矢張り未成年の幼さを残していた。
お別れパーティに関して、一部の新聞で、高校生なのにアルコール飲料を飲んでいたと報じたところがあった。会場にアルコール飲料があったのは事実だが、それは国際アマチュア演劇連盟の役員と審査員を務めた劇評家、その他の来賓席に出ていたのである。また日本の参加高校でも、いわゆるOB、OGといわれる人たちが沢山参加していたので、その人たちが自席に持ち込んでいたのかもしれない。主催者としては決して高校生にアルコール飲料を給したことはなかった。その点は厳に留意していたところである。舞台上での飲酒を巡っての討論会でのやり取りがあった後だけに、「飲酒文化」について考えさせられるところがあった。
この高校演劇祭で言っておかねばならないのは、富山の高校生諸君による演劇祭新聞が発行されたことである。もちろん、高校の先生たちと北日本新聞の佐伯記者が親しく指導されたこともあったからだろうが、連日遅くまでねばって、翌日には公演のことから、身振り手振り入りで取材した色んな記事を掲載した新聞「たてやま」は大好評であった。だが、シェイクスピアの「オセロー」に出てくるイアゴーの科白'I am nothing, if not critical.'(批判しなけりゃ、俺の取り所は無しだ)ではないが、やたらとcritical「批判的」であることが新聞の本態だと錯覚されている向きもあるらしく、そうした誤解に発する食い違いもあったが、全体として高校生諸君の健闘を称えておきたい。
お別れパーティに関して、一部の新聞で、高校生なのにアルコール飲料を飲んでいたと報じたところがあった。会場にアルコール飲料があったのは事実だが、それは国際アマチュア演劇連盟の役員と審査員を務めた劇評家、その他の来賓席に出ていたのである。また日本の参加高校でも、いわゆるOB、OGといわれる人たちが沢山参加していたので、その人たちが自席に持ち込んでいたのかもしれない。主催者としては決して高校生にアルコール飲料を給したことはなかった。その点は厳に留意していたところである。舞台上での飲酒を巡っての討論会でのやり取りがあった後だけに、「飲酒文化」について考えさせられるところがあった。
この高校演劇祭で言っておかねばならないのは、富山の高校生諸君による演劇祭新聞が発行されたことである。もちろん、高校の先生たちと北日本新聞の佐伯記者が親しく指導されたこともあったからだろうが、連日遅くまでねばって、翌日には公演のことから、身振り手振り入りで取材した色んな記事を掲載した新聞「たてやま」は大好評であった。だが、シェイクスピアの「オセロー」に出てくるイアゴーの科白'I am nothing, if not critical.'(批判しなけりゃ、俺の取り所は無しだ)ではないが、やたらとcritical「批判的」であることが新聞の本態だと錯覚されている向きもあるらしく、そうした誤解に発する食い違いもあったが、全体として高校生諸君の健闘を称えておきたい。
| 戻る | 目次へ戻る | 次へ |